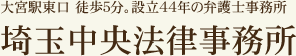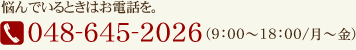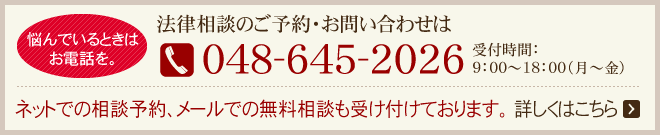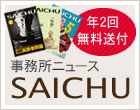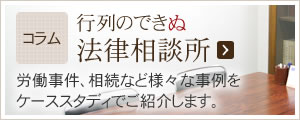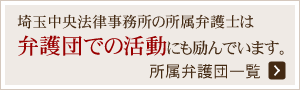![]()
将来的に自分の判断能力が低下してしまったときに備えて、判断能力のある内に、後見事務の内容と、後見人になってもらう人(任意後見人)を、契約によって決めておく制度です。
つまり、今はなんとか大丈夫だけれど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、そうなったらどうしよう、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、いよいよ認知症になってしまったという時に家庭裁判所に申し立てをして、後見事務をスタートさせるという制度です。
具体的には、「任意後見監督人(任意後見人の仕事を監督する人)の選任」を家庭裁判所に申立てることによって、後見事務がスタートします。
なお、任意後見契約は、内容を自由に決められますので、任意後見人を誰にするか、どの範囲の後見事務を委任するかは、自由に決めることが出来ます。
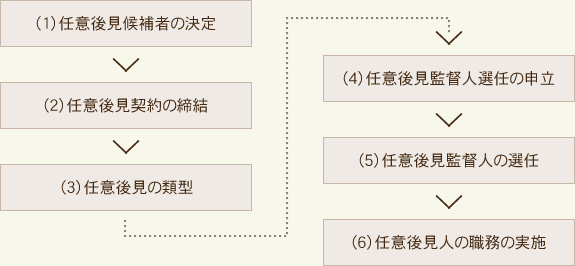
(1)任意後見候補者の決定
まずは、将来的に、自分の財産管理や身の回りの手続を依頼したい人を決め、依頼する内容について話し合いをします。
(2)任意後見契約の締結
本人と任意後見候補者との間で、話し合った内容についての任意後見契約を、公正証書を作成して行います。
公正証書は、約2万円ほどの費用で、公証人役場で作成します。
(3)任意後見の類型
任意後見契約を締結した後の流れは、任意後見の類型によって異なります。
■将来型
任意後見の典型的な形であり、将来、本人の判断能力が低下した時点で、任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見人の職務がスタートするという類型です。
■即効型
本人の判断能力が既に低下している状況で、任意後見契約締結後、直ちに、任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見人の職務がスタートするという類型です。
■移行型
本人の判断能力が低下するまでは、財産管理委任契約により、任意後見人候補者に財産を管理してもらい、本人の判断能力が低下した時点で、任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見人の職務がスタートするという類型です。
(4)任意後見監督人選任の申立
本人(被後見人)の判断能力が低下した時点で、本人、配偶者、4親等内の親族や任意後見人受任者によって、任意後見監督人選任の申立を管轄の家庭裁判所に行います。
申立書のほかに、戸籍謄本、診断書等の書類が必要です。
(5)任意後見監督人の選任
裁判所によって、任意後見監督人選任の審判がなされ、これにより、任意後見人の職務が開始されます。
任意後見人は、法定後見人と同じように、包括的代理権を有し、被後見人本人に代わって財産管理を行い、施設への入所契約等の身上監護面でもサポートします。
任意後見人の報酬は任意後見契約に定められた金額が月々発生し、被後見人の財産から支払われます。
任意後見監督人の報酬は、裁判所の決定により付与されます。
(6)任意後見人の職務の実施
後見監督人選任の審判により、任意後見がスタートします。
後見人は、任意後見契約に沿って、被後見人本人に代わって預貯金や不動産の管理、税金等の支払い等の財産管理を行い、施設への入所契約等の身上監護面でもサポートします。
後見人には、任意後見契約によって定められた後見人報酬が支払われます。
契約締結手数料
財産等の内容により、10万~20万円程度(税別)。
委任事務処理を行う場合
委任内容により、協議の上、決定します。